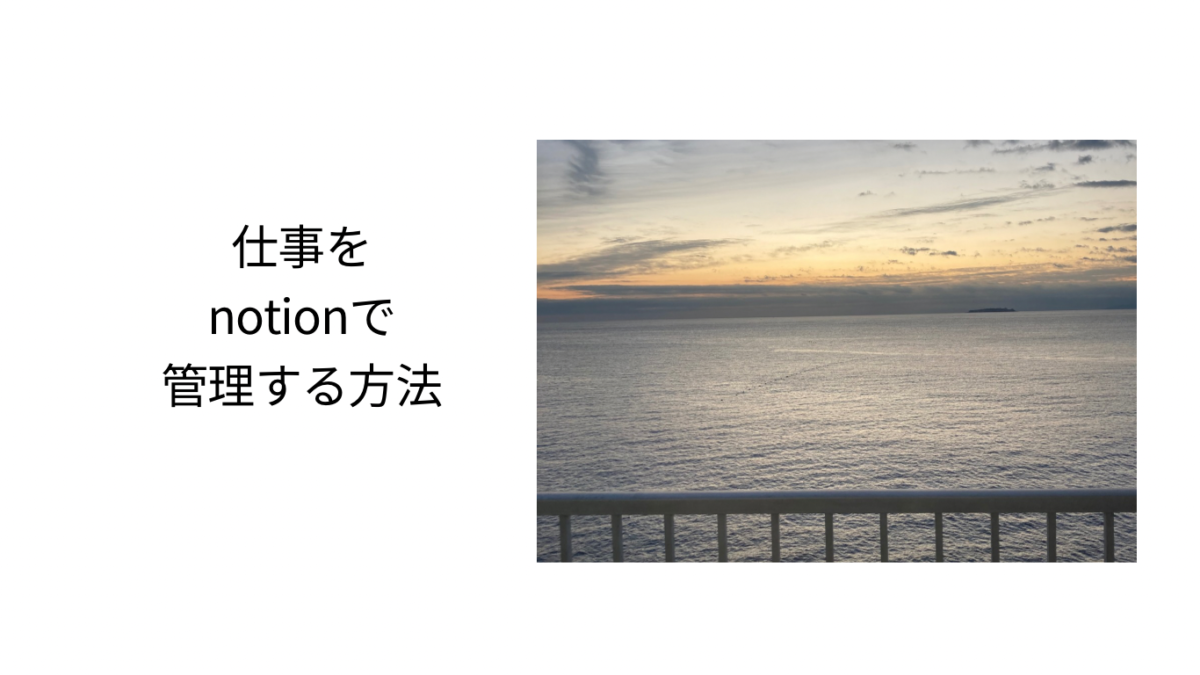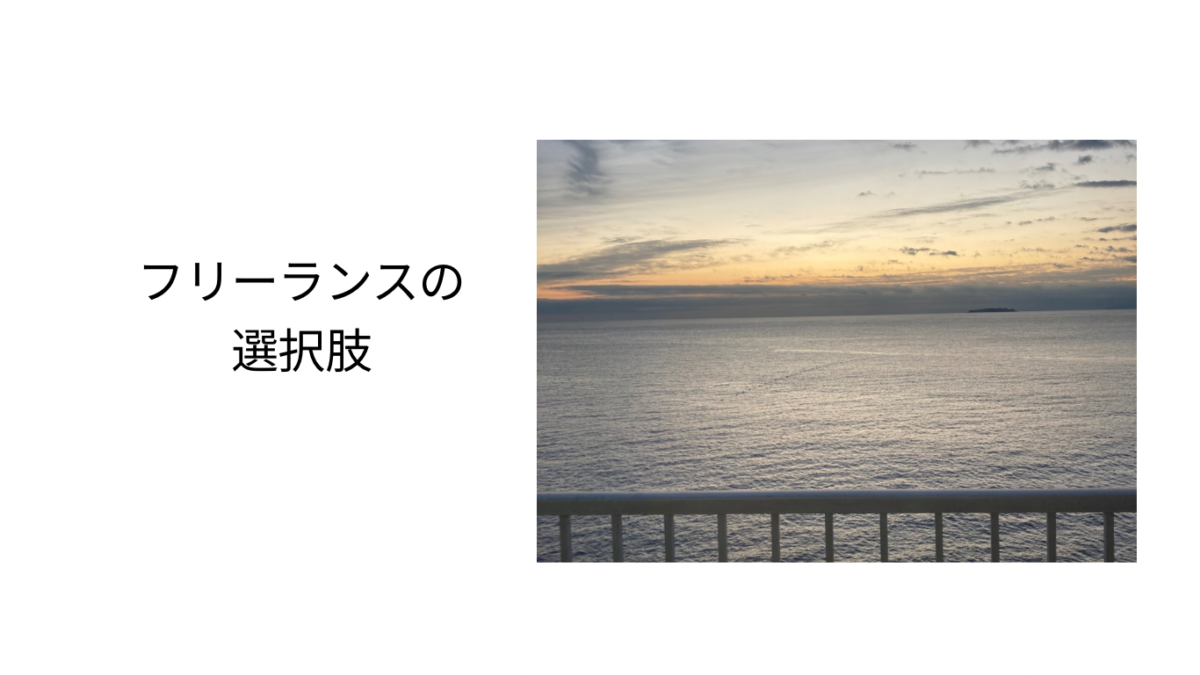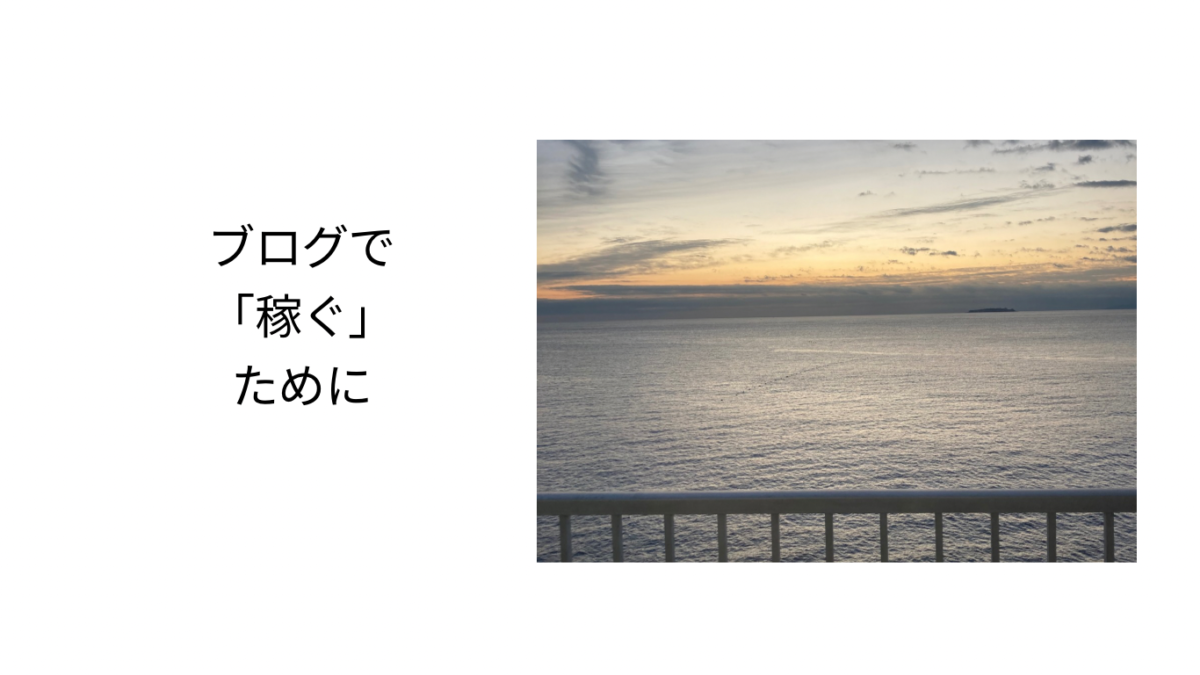こんにちは、こんばんは、mariです。
今日は取り組んでみてよかったこととして、notionの活用についてお話ししようと思います。
自分自身の名前で仕事を引き受けていく上で、仕事の管理は今まで以上に重要です。管理ツールとして、手帳やgoogleカレンダーを利用している方もいるでしょう。
わたしは断然、notionの活用をおすすめします!
理由は2つ。
①情報を一元化することで「どこに何の情報がある」かわかりやすい
(管理のしやすさ)
②他アプリとの連携もとりやすく、業務効率化につながる(
手軽さ)
という2点です。
実際に作成したnotionの画像を挟みつつ、お話ししていきます。
notionってどんな製品?
notionは無料で使えるドキュメントサービスです。もともとnotionが作られた理由として「All in one workspace」という考え方があります。
(参考)Notion公式HPより
「タスクリスト、製品ロードマップ、デザインリポジトリーなど、必要なものすべてを集約させたのです。レゴブロックのように、パーツを組み合わせて自分だけのワークスペースを構築することもできます。」(notion公式HPより引用)
このとおり、
①どんな形式にも合わせてドキュメントを作成しやすい
→個人的なタスク管理をはじめとして、(具体的なプロダクト商品がある場合は)商品についても「記載したい」方法で記入しやすい
②ブロックを組み立てるような組み合わせができるので、自由度が高い
→操作が感覚的にわかりやすい、作りがシンプル
という点が非常に特徴的で、使いやすい理由です。
どのように使っているの?
普段わたしが使用しているnotionを利用してお話ししていきます。

大きな構成として3つに分けています。
①ポートフォリオ
(動画やライティングの作品をここにまとめている)
②ツールマニュアル
(ツールもスキルの1つとなるので、わからないことがあればここにまとめている)
③仕事管理用
といった感じです。③の仕事管理用は、契約先と「notionを見ながら」打ち合わせが出来る仕様にしています。
具体的にお話しをすると、
・仕事の予定「他の業務と被らないか?」→カレンダー機能を活用
・売上の状況→「売上ページ」でfreeeを繋いで管理
・お客様に伝える情報→基本情報に全てメモ
・ルーティーンタスクの管理→MUST業務に記載(予定、手順ともに)
というようにしています。
それぞれのページに「アイコン」をつけて、ページを独立させることができる点も非常に便利です。
どこまでnotionで管理しているの?
基本的には、自分のアイディアから契約金額まで「すべて」をnotionで管理しています。
とくに「アイディア」は、ケータイにもnotionアプリ、notionカレンダーをDLしています。情報を書く場所を1つに集約するためです。
そうすると、急いでいる時にも開いて記入しやすいです。
また、notionは幅広いアプリと連携可能です。なので、使用している会計ソフトfreeeを連携しています。
経理周りの業務などはルーティーン業務が多いので、手順をみながらすぐにアクセスできた方が便利です。
このような特徴が業務効率が良くなると考える点です。
会社をより大きくしたい人に、特におすすめ
わたしのように、完璧に個人で活用する人にも利便性があることは確かです。
ですが、共同作業ができる点や(HPに招待すれば)複数人で閲覧可能な点も、利便性の高さの1つです。業務効率の話にもつながるでしょう。
会社で「人を雇う」決断をするときは、何かしら業務の人手不足だからだと推察できます。
その点を考慮すると、
①すでに決めたこと(プロセスも含めて言語化できていると尚良い)
②手順を守って対応したいこと
など、認識を合わせておきたい項目についても、タイムリーに記入し、記録として残せます。
つまり、「人が入るから資料を整備しなくては」という状況になりにくいです。
もちろん資料の整備の必要も出てきますが、個人的には後から作成するよりは楽な気がします。
後々人が増えるかもしれない、という人にもnotionはおすすめです。
まとめ
わたしは元々アナログ派で、ノートや手帳に情報をまとめるのが好きでした。
ですが、状況によっては雑に書いてしまい、あとから読み返してわからなかったり、
時にはどこになにを書いたっけ、とわからなくなったこともあります。
これらの経験を踏まえると、notionの各機能は非常に画期的です。
個人のtodoリストとしても活用できますし、複数人でプロダクトを運用している場合にも、共通認識を合わせる場として活用できます。
公式HPに、基本的な使用方法についても掲載があるので、この点も魅力です。
わたしも公式HPでnotionを学んだうちのひとりです。
良ければ、一度手にとってみてください。
それではまた次の記事でお会いしましょう。