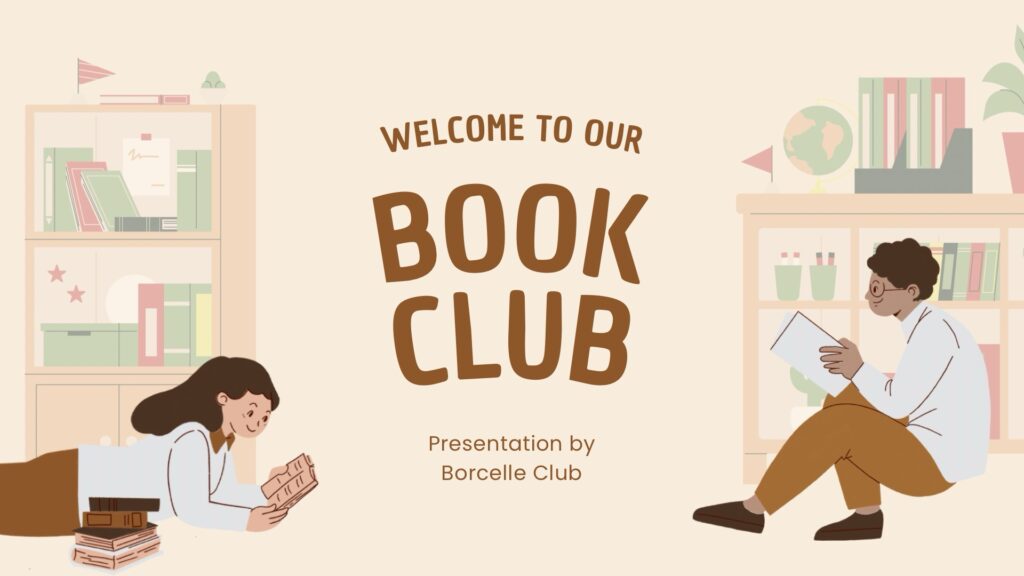こんにちは、こんばんは、mariです。
昨日に引き続き、体のことに感じて調べ物をして、書いてまとめていくスタイルで進めます。本日は筋膜についてです。
筋膜のイメージとしては、食品をイメージすると、とてもわかりやすいです。お肉コーナーに売っている鶏肉などは、お肉の上に、うすい膜が張っているもよもあると思います。鶏肉同様に、人間にも薄い膜が張っています。膜には2種類ありますが、それは後ほど触れます。人間の筋肉のまわりの膜は筋膜といい、洋服のシワのように筋膜が一部に偏ってしまうと、コリなどの不調として体に出てきます。こちらもヨガの先生に教わりました。ヨガやピラティスのように、体を動かすスポーツの観点から筋膜について話すと、膜の偏りをなくすように体をほぐすことが、コリの解消に繋がります。より安全に、体を動かすことができるのです。
これからは解剖学的な観点から、筋膜を見ていきます。手元にあるターザンから得た知識を、簡単にまとめていきます。近年、筋膜には体の状態をモニタリングし、筋肉に伝えるという役割を果たしているということがわかりました。そこで、トレーニングを行う上でも、筋膜と筋肉をセットで捉えた方が、効果が上がると捉えられています。
また、筋膜は第二の骨格とも呼ばれており、体の内臓や血管、神経なども覆っているとのことでした。